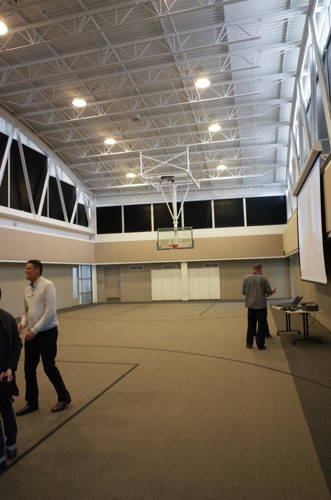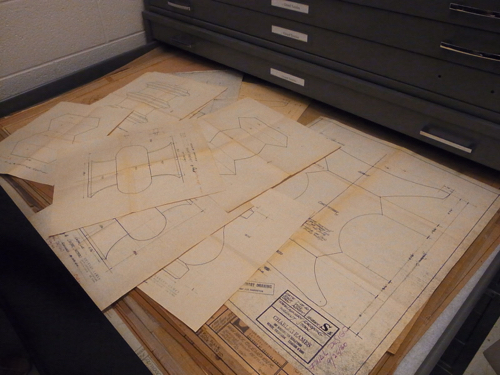ライター渡部のほうです。
インドネシア、ジョグジャカルタ。伝統的な市場のブリンハルジョ市場。混沌としていて分かりにくいのだが2階建てと3階建ての二棟からなっていて、合計4.5ヘクタール(東京ドーム1個分)、店舗数5000軒だとか。サイズに関しては、資料が少ないので、正確なところは分からない。しかも屋外にも露店が広がっているので、ますます分からない。
正面入口から入るとバティック、布類ばっかりなのだが、ずんずん進んでいくと、生活雑貨、生薬、機械類(オートバイのパーツなど)、精肉、食品、など、市民生活を支えるものとなっている。
主に食品をどのように「包む」のか、見てみた。
簡易食堂。
![b0141474_0112614.jpg]()
食堂っつーか、おかずが並べてあるだけ、という言い方もあるけど、作り手(売り手)がいて、おかずがあって、お客が来れば、もうそこは食事処。
四角に切ったバナナの葉は、おかずを並べたり、おかずの上に置いて埃や虫を避けたり、持ち帰りの時に包む包み紙になったりする。
包んだモノの写真を撮ってこなかったのが残念だが、しかも文章で説明しようと色々書いてみたのだが、なんとも写真がないと分かりづらい話なので、ここではやめておこう。色んな屋台や食堂を見たが、包み方はそんなに決まってない様子。四角錐っぽい形になったり、平べったい形になったり、包むモノにより多様。しかし、かなり汁っぽいものもきちっと包み込める技術がすごい。
この「お包み技術」が継承され、市販品の紙包み商品に活かされているのだと感じた。
葉っぱと言えば、この魚のカゴ(?)がすごい。
![b0141474_1425338.jpg]()
サイズ感分からなすぎだけど魚のサイズ10センチくらい。
iPhoneより小さい魚の箱、だとお考え下さい。
ビニール袋入り総菜。
![b0141474_1313980.jpg]()
広い市場で働く人向けに、狭い路地も通り抜けられるような小さいカート(というか家庭用ワゴンにカゴを乗っけただけだけど)でおかずを売っている。
ビニール袋に汁物が入っているが、きっちちゴム止めされ、こぼれてない。
タイでもそうだが、くるくるっと輪ゴムを止めるだけで、なんであんなにこぼれないようなビニール包みができるのか、よく不思議に思う。
あらかじめ袋に入っているもの。
![b0141474_13481120.jpg]()
![b0141474_13482452.jpg]()
上はテンペを揚げたスナック、下の左側は日本のイカ天スナックみたいな、ウナギ天。
市場で一番よく見るのは、透明なビニールの袋に、商品や店名を印刷した紙を商品と一緒に入れる上のタイプ。あるいは、下の写真右側のようなそうした紙でビニール袋にホチキスで留めるタイプ。
下の写真左側の下のほうになってしまったが、ビニールに直接印刷されているものもある。
決まった商品が、決まったサイズで入るのが分かっている量産品は、袋に印刷されているものも多いのだが、基本計り売りが多いゆえ、対応しやすい透明ビニール+印刷された紙、の組み合わせ。
これはお菓子屋。
![b0141474_1463017.jpg]()
プラスチックの入れ物に入っているものを計り売りする。
揚げ物や食品を透明ビニールやプラスチック容器に入れて、露天に出す、というのは、油焼けしやすいだろうし、今の日本ではなかなか見ない。ただし、透明なのは、コストの安さからだけではない。
工場製、量産されたものを販売するスーパーマーケットなどではなく、実物を見て買う市場では、その実物がどういうものであるか、目で見て確かめる、ということも重要である。
私が子供の頃は、ポテトチップスなどのスナックが透明な窓のあった袋から中身の見えないアルミ蒸着フィルムに変わった移行期で、中身が見えなくて割れていないか不安だ、と思った覚えがあるのだが、いまではすっかり普通。中身が見えなくても大丈夫、と思わせる。あるいはそう思わせられている、とも言えるけど。
パッケージデザインは、中身がどういうものであるか、を代弁する機能がなくてはならない。店の写真に映っている店主のおじさんの役目を果たさなくてはならないわけだ。
現状のインドネシアでは、市場もあれば、個人商店もスーパーマーケットもある。
スーパーマーケットも随分普及してきているが、値段の面から見ると、圧倒的に市場のほうが安い。
では、パッケージされた商品には、(モノによっては、だけど)倍以上する値段を意味や価値をいかに伝えられるのか。
ただきれいなパッケージでは訴求しない。このブランドなら、この説明なら確信して買える、と消費者を説得しなければならない。
今のインドネシアの食品、日用品はそういった状況なのだ。
その他、市場で見て気になったもの。
このハンガー、丸い輪っかはどう使うんだろう、なんか便利っぽいけど、邪魔なような気もするし。
![b0141474_14264184.jpg]()
市場は、それぞれの商店主が朝やって来て、店を開く。シャッター式になっているところもあるが、タンス式とでも言えばいいのだろうか、
![b0141474_14285512.jpg]()
すでに収納されていて、朝、鍵を開け、扉を開き、商品を出せば商店になる。
下の収納部分は閉めて、その上に座っている店主もいるし、全部開けて、前に椅子を置いて座っている店主もいる。ミニマル住宅みたいだ。
インドネシア、ジョグジャカルタ。伝統的な市場のブリンハルジョ市場。混沌としていて分かりにくいのだが2階建てと3階建ての二棟からなっていて、合計4.5ヘクタール(東京ドーム1個分)、店舗数5000軒だとか。サイズに関しては、資料が少ないので、正確なところは分からない。しかも屋外にも露店が広がっているので、ますます分からない。
正面入口から入るとバティック、布類ばっかりなのだが、ずんずん進んでいくと、生活雑貨、生薬、機械類(オートバイのパーツなど)、精肉、食品、など、市民生活を支えるものとなっている。
主に食品をどのように「包む」のか、見てみた。
簡易食堂。

食堂っつーか、おかずが並べてあるだけ、という言い方もあるけど、作り手(売り手)がいて、おかずがあって、お客が来れば、もうそこは食事処。
四角に切ったバナナの葉は、おかずを並べたり、おかずの上に置いて埃や虫を避けたり、持ち帰りの時に包む包み紙になったりする。
包んだモノの写真を撮ってこなかったのが残念だが、しかも文章で説明しようと色々書いてみたのだが、なんとも写真がないと分かりづらい話なので、ここではやめておこう。色んな屋台や食堂を見たが、包み方はそんなに決まってない様子。四角錐っぽい形になったり、平べったい形になったり、包むモノにより多様。しかし、かなり汁っぽいものもきちっと包み込める技術がすごい。
この「お包み技術」が継承され、市販品の紙包み商品に活かされているのだと感じた。
葉っぱと言えば、この魚のカゴ(?)がすごい。

サイズ感分からなすぎだけど魚のサイズ10センチくらい。
iPhoneより小さい魚の箱、だとお考え下さい。
ビニール袋入り総菜。

広い市場で働く人向けに、狭い路地も通り抜けられるような小さいカート(というか家庭用ワゴンにカゴを乗っけただけだけど)でおかずを売っている。
ビニール袋に汁物が入っているが、きっちちゴム止めされ、こぼれてない。
タイでもそうだが、くるくるっと輪ゴムを止めるだけで、なんであんなにこぼれないようなビニール包みができるのか、よく不思議に思う。
あらかじめ袋に入っているもの。


上はテンペを揚げたスナック、下の左側は日本のイカ天スナックみたいな、ウナギ天。
市場で一番よく見るのは、透明なビニールの袋に、商品や店名を印刷した紙を商品と一緒に入れる上のタイプ。あるいは、下の写真右側のようなそうした紙でビニール袋にホチキスで留めるタイプ。
下の写真左側の下のほうになってしまったが、ビニールに直接印刷されているものもある。
決まった商品が、決まったサイズで入るのが分かっている量産品は、袋に印刷されているものも多いのだが、基本計り売りが多いゆえ、対応しやすい透明ビニール+印刷された紙、の組み合わせ。
これはお菓子屋。

プラスチックの入れ物に入っているものを計り売りする。
揚げ物や食品を透明ビニールやプラスチック容器に入れて、露天に出す、というのは、油焼けしやすいだろうし、今の日本ではなかなか見ない。ただし、透明なのは、コストの安さからだけではない。
工場製、量産されたものを販売するスーパーマーケットなどではなく、実物を見て買う市場では、その実物がどういうものであるか、目で見て確かめる、ということも重要である。
私が子供の頃は、ポテトチップスなどのスナックが透明な窓のあった袋から中身の見えないアルミ蒸着フィルムに変わった移行期で、中身が見えなくて割れていないか不安だ、と思った覚えがあるのだが、いまではすっかり普通。中身が見えなくても大丈夫、と思わせる。あるいはそう思わせられている、とも言えるけど。
パッケージデザインは、中身がどういうものであるか、を代弁する機能がなくてはならない。店の写真に映っている店主のおじさんの役目を果たさなくてはならないわけだ。
現状のインドネシアでは、市場もあれば、個人商店もスーパーマーケットもある。
スーパーマーケットも随分普及してきているが、値段の面から見ると、圧倒的に市場のほうが安い。
では、パッケージされた商品には、(モノによっては、だけど)倍以上する値段を意味や価値をいかに伝えられるのか。
ただきれいなパッケージでは訴求しない。このブランドなら、この説明なら確信して買える、と消費者を説得しなければならない。
今のインドネシアの食品、日用品はそういった状況なのだ。
その他、市場で見て気になったもの。
このハンガー、丸い輪っかはどう使うんだろう、なんか便利っぽいけど、邪魔なような気もするし。

市場は、それぞれの商店主が朝やって来て、店を開く。シャッター式になっているところもあるが、タンス式とでも言えばいいのだろうか、

すでに収納されていて、朝、鍵を開け、扉を開き、商品を出せば商店になる。
下の収納部分は閉めて、その上に座っている店主もいるし、全部開けて、前に椅子を置いて座っている店主もいる。ミニマル住宅みたいだ。